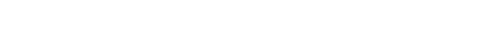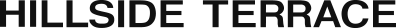ヒルサイドテラスの“住人”たち Part3
第1回 「映画プロデューサーという仕事」 阿部秀司(映画プロデューサー)
- SEMINAR
- 募集終了
このイベントは終了しました
| 出演 | 阿部秀司(映画プロデューサー) |
|---|---|
| 日時 | 2012年04月26日(木) 19:30-21:00 |
| 会場 | ヒルサイドバンケット(ヒルサイドテラスC棟) |
| 定員 | 70名 |
| 会費 | 一般2,500円 クラブヒルサイド会員/学生1,500円(ドリンク付) |
| 予約・問合せ | ヒルサイドインフォメーション TEL: 03-5489-3705 FAX: 03-5489-1269 E-MAIL : mail info@hillsideterrace.com |
出演者

阿部 秀司
映画プロデューサー、阿部秀司事務所・代表取締役、ROBOT創業者・顧問。1949年東京都出身。
慶応義塾大学法学部卒業後、1974年に第一企画入社。コピーライター、CMプロデューサー、クリエイティブ・ディレクターとして活躍後、1986年映像制作会社ROBOTを設立。1995年に映画『Love Letter』を機に映画事業をスタート。その後も、プロデューサーとして、『ジュブナイル』、『Returner』、『K-20 怪人二十面相・伝』、『ALWAYS 三丁目の夕日』シリーズ、『RAILWAYS』シリーズをはじめとした多くの作品を世に送り出している。とくに『ALWAYS 三丁目の夕日』では、日本アカデミー賞最優秀作品賞など国内の数多くの映画賞とともに、プロデューサーへの賞である藤本賞・特別賞、エランドール賞を受賞。2010年3月ROBOTを退職、創業者・顧問に就任。同年7月「阿部秀司事務所」を設立。これまでに数多くの若き優秀な映画監督をデビューさせており、主な監督として、岩井俊二、山崎貴、本広克行、羽住英一郎、加藤久仁生、小泉徳宏がいる。
著書に『じゃ、やってみれば “感動という商品”を創り続ける男の言葉36』(日本実業出版社)。
関連シリーズ
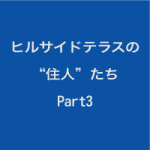
ヒルサイドテラスの“住人”たちPart3 2012年~
ヒルサイドテラスを拠点に活躍する“住人”にその仕事と人生を語っていただく大好評のセミナーシリーズ。1年ぶりの本シリーズでは、映画、広告、音楽、美容、写真など、多様な分野の第一線で活躍する新しい“住人”の方々にスポットを当てます。
- 第1回 「映画プロデューサーという仕事」阿部秀司(映画プロデューサー)終了しました
- 第2回 「代官山をより面白くするアイデアを考える」 伊藤直樹(クリエイティブディレクター/PARTY)終了しました
- 第3回 「僕はこうして音楽家になった」渋谷慶一郎(音楽家/作曲家)終了しました
- 第4回 「嶋田ちあきの創る美の世界」嶋田ちあき(ヘアメイクアップ・アーティスト)終了しました
- 第5回 「風景を記述する試み」新津保建秀(写真家)終了しました
- 第6回 「心臓からのメッセージ」須磨久善(心臓外科医)終了しました
- 第7回 「キギのこれまでとこれから」 原亮輔+渡邉良重/キギ(アートディレクター)終了しました
ヒルサイドテラスの“住人”たち Part3 レポート 第1回 「映画プロデューサーという仕事」 阿部秀司

1年ぶりに再開された「住人シリーズ」は、トップバッターとして、日本を代表する映像制作会社「ROBOT」の創業者であり、映画プロデューサーとして数々のヒット作を送り出してきた阿部秀司さんをお迎えしました。邦画が長い低迷期に入り始めた頃に、あえて映画の道に入られた阿部さんの、映画への愛と情熱があふれるお話をおうかがいすることができました。
映画産業がどのような仕組みによって成立しているのか、アメリカの映画産業と日本の映画産業の構造的な違い、圧倒的なハリウッド映画の興行力に対して、それでも日本映画が世界の映画市場に打って出る可能性はあるのか、など興味深いお話が続きました。
阿部さんはまた、最初の映画「Love Letter」で岩井俊二監督を、「ALWAYS三丁目の夕日」で山﨑貴監督を、「踊る大捜査線 THE MOVIE」で本広克行監督を世に送り出すなど、若く優れた才能を見出すことでも知られています。お話をうかがいながら、随所に垣間見えるあたたかで優しいお人柄こそが、こうした若い世代を応援しようというお気持ちにつながり、彼らの活躍の場をつくりだしているのだということがよくわかりました。
「映画とは体験である」と語る阿部さん。映画館での2時間は、お茶の間のテレビモニターでDVDを楽しむこととは決定的に違います。映画館に行くとは、それ自体が能動的な文化的行為であり、そうした私たちのあり様が日本の映画を支えることになるのです。阿部さんのお話から、「映画館に行こう」と強く思いました。
現在は次回作を準備中とのこと。「手のひらに未来がある」子どもたちのためにも、団塊の世代のためにも、ますます素晴らしい映画をつくっていただきたい、心から応援したいと思うセミナーでした。