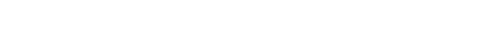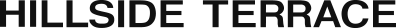キューバ学校 第1期
- SERIES
2008年末から09年初頭にかけて、キューバは革命50周年を迎えます。
カストロやゲバラなど、現代世界を語るうえで欠かせない人物も生み出したキューバ革命とは、
何だったのでしょうか。ビデオ上映、詩の朗読、絵画作品の展示、DJの案内によるキューバ音楽鑑賞など、
多面的なプログラムをお届けします。
| 案内人 | 太田昌国(民族問題研究家) |
|---|---|
| 会期 | 2008年5月~2009年1月 |
| 主催 | キューバネットワーク/現代企画室 |
| 共催 | クラブヒルサイド |
スケジュール
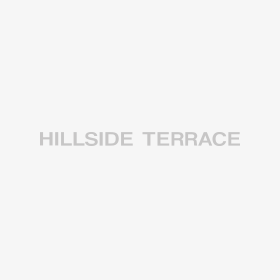
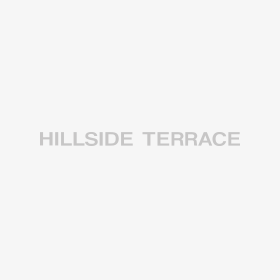
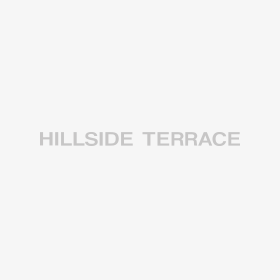
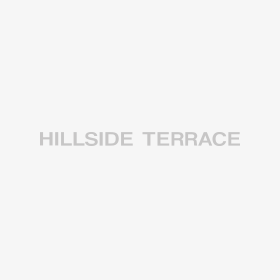
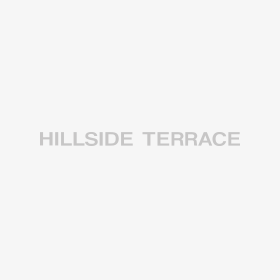
登壇者・講演者
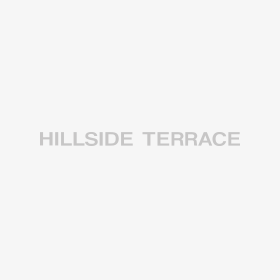
案内人:太田昌国
1943年釧路市生まれ。東京外語大でロシア文学・ロシア革命史を学んだ後、数年間にわたるラテンアメリカ地域放浪の旅を経て第三世界研究に従事する一方、現代企画室の編集者として人文書の企画・編集に関わる。著書『ゲバラを脱神話化する』『〈異世界・同時代乱反射〉『「国家と戦争」異説』『暴力批判論』『「拉致」異論』など多数。
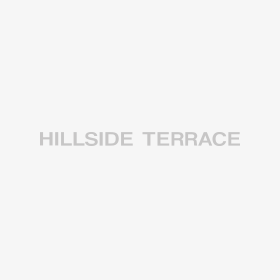
富山妙子
1921年神戸市に生まれ、少女時代を旧満州、大連とハルビンで過ごす。女子美術大学に学ぶが、アカデミズムとぶつかり除籍。戦後、画家の社会参加の形として炭鉱をテーマに創作活動。第三世界への旅の体験に基づく制作や金芝河の詩をテーマにした創作活動を経て、絵のシリーズを映像化する独自の世界を切り開く。スライド『しばられた手の祈り』『海の記憶』、著書『戦争責任を訴えるひとり旅』『解放の美学』『はじけ!鳳仙花』『silenced by history』など多数。
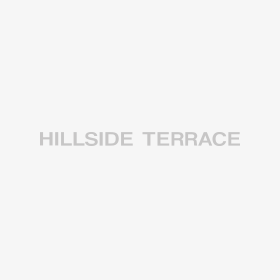
越川芳明
明治大学教授(現代アメリカ文学)。米墨国境地帯を精力的にフィールドワークして、 ラテンアメリカの視線から「アメリカ」を読解する。著書に『トウガラシのちいさな旅』(白水社)、『ギターを抱いた渡り鳥』(思潮社)など。
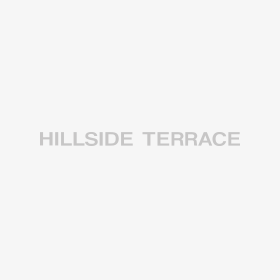
波津博明
札幌生まれ。1987―90年、読売新聞リオデジャネイロ特派員として、ラテンアメリカ全域を取材。 その後ローマ支局、解説部などを経て、2006年大妻女子大学教員。関心分野はほかにSF、イタリア音楽など。
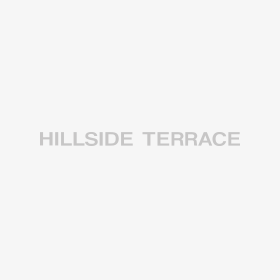
岩村健二郎
早稲田大学法学部講師(歴史学)。キューバの歴史学、思想史が専門。Grupo Chevere、Salsa Swingozaなどのグループで歌を担当。近業に共著『キューバを知るための52章』(明石書店)、「“キューバ文化”はいかに模索されたか」(『世界地理講座 第14巻 ラテンアメリカ』朝倉書店)、Salsa Swingoza『Aqui se puede』(EWCD-0136)、Grupo Chevere『CheveRenacer』(DML-071021)など。
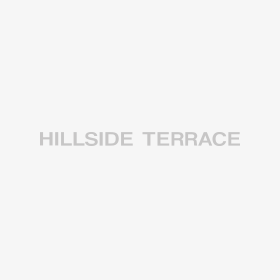
アベル・バロッソ(アーティスト)
1971年、ピナール・デル・リオ(キューバ)生まれ。
キューバ国立芸術学院に学ぶ。木版画の技法を用いたインスタレーション作品の数々は、キューバ社会の現状をテーマに、グローバリゼーションや情報化社会のもたらした現代の抱える様々な問題を独特な視点から暗喩し、国際的に注目を浴びている。主な作品に「第三世界のインターネットカフェ」(第7回ハバナ・ビエンナーレ招待作品)、「冷戦は終わった! Let's enjoy the age of Globalization」などがある。
キューバ国内はもとより、海外ではカナダ、ドイツ、アメリカ、イギリスなどで個展を開催。今回で2度目の来日となる滞在中に、「YOMOYAMAEXHIBITION 2008」(四方山荘アーティスト・イン・レジデンスプログラム)、「アベル・バロッソ展」(ギャラリー プロモアルテ)を開催。